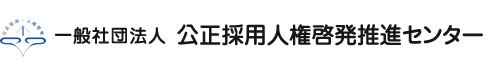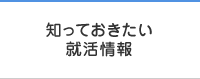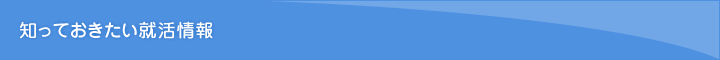【就活考転載】AIを活用した採用 賢い補佐役、最終責任は人 曽和利光(2025/9/22付 日本経済新聞 夕刊)(2025/09/30)
生成AI(人工知能)の登場などAIの進化は、採用や就活の状況を大きく変えつつある。例えば年間数万件にも及ぶエントリーシート(ES)を処理しなければならない大手企業の人事部門にとって、AIは便利な道具となっている。ESの自動仕分けや動画面接の評価などは既に広がり始め、人事担当者が本来注力すべき戦略的な業務に時間を割けるようになった。
効率化という効能のみにとどまらず、AIは採用評価の公平性を高める可能性も秘めている。人間が無意識に持つ心理的バイアス、たとえば学歴や性別などといった属性に左右されにくくなるからだ。もし評価基準の設計が的確であれば、これまで埋もれてきた人材を発掘することができるかもしれない。
とはいえ、よいことばかりではない。AIは過去のデータから学習するため、そのデータ自体が偏っていれば、偏りを未来にコピーしてしまう。実際、特定大学出身者ばかりを採用してきた会社だと、AIはむしろその傾向を強めかねない。
さらに困るのは「なぜこの人を落としたのか」が見えにくくなる点だ。人事の世界では説明責任は避けて通れない。不合格の理由を語れない選考は学生の信頼を損なうだけでなく、社内からも疑問の目を向けられる。
就活生の行動も変化している。AIに見抜かれることを意識するあまり、「AIにウケる」表現や回答を意図的に選ぶ学生も増えている。場合によっては、その対策自体もChatGPTなどの生成AIを使って行われている。
その結果、個性が薄まり「どこかで見たような受け答え」をする人ばかりになる危険もある。従来の「面接官に合わせた演技」が「AIに合わせた演技」に置き換わっただけでは、マッチングの精度は向上しない。
こうした現実を踏まえると、現時点では、AIの役割はあくまで人間の意思決定の補助にとどめるべきだろう。情報収集や整理、そして明らかな偏見の除去といった前処理に活用するのにはとても有効だが、最終的に「採用するかどうか」を判断するのは人間だ。
採用とは単なるスキル評価にとどまらず、「この人と一緒に働きたいか」「うちの組織や職場に合うか」といった、データでは捉えにくい要素を含む未来志向の意思決定だ。この判断には人間の経験、洞察、そして最終的な責任や覚悟が不可欠である。これは人間にしかできない。
AIは人間の役割を奪うわけではない。むしろ、人間にしかできない関係構築や人の動機付けに力を注ぐ余地を広げる。その意味でAIは脅威ではなく、採用の専門性をより深めるための機会と捉えるべきだ。強力な道具であることに間違いはないが、なんでもできるわけではない。人間が最終責任を持つことを前提に、賢い補佐役として位置づけるのが妥当であろう。
(人材研究所代表)