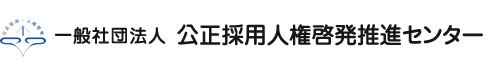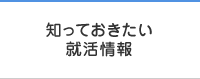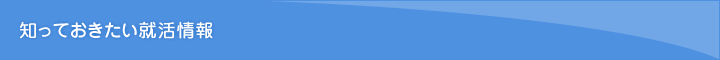【就活考転載】少子化でも競争激しく 進学率上昇で大学生増加 上田晶美(2025/9/29日本経済新聞 夕刊)(2025/10/07)
内定の報告に来てくれた大学4年の女子学生に「お疲れさまでした。就活を振り返ってみてどうでしたか」と尋ねたところ、「長かったです。もっとすぐに決まると思っていたのに、少子化だから就活は楽かと思ったら、そんなことはなかった」という感想だった。
「長かった」というが、彼女の場合、なかなか内定が出なかったというのではない。先に出た内定で安易に決めてしまわず、納得いくまで受け続けたということだ。その努力は素晴らしく、健闘をたたえた。
新卒の就活を毎年見ていて思うのは、少子化といえど「就活はそう楽にはならないな」ということである。だがこの少子化という単純化が、社会一般の目をくらませていると感じる。
確かに少子化は大きな社会問題で、出生率はぐんぐん減ってきている。1990年頃には年間約120万人生まれていた子どもが、昨年は70万人を割り込んでしまっている。
私が現在の仕事を始めたのが93年。30年余り就活を見てきて思うのは、少子化で売り手市場といっても、就活は楽にはなっていないということだ。エントリーシートを何枚も提出し、筆記試験を受け、面接も1回では済まない。一部オンライン化したことで楽になった部分もあるが、またその対策も必要になった。
こうした就活の選考過程にも問題はあるとは思うが、そもそも少子化といっても大学生の数は減っておらず、むしろ増えているという事実をご存じだろうか。ここが盲点である。大学進学率は90年は20%台半ばで50万人弱だったのに対し、近年は進学率が50%台後半で60万人超と逆に増えている。大学の卒業生はむしろ増えているのだ。
競争は激化している。進学率の大きな転換点は、91年の国による大学設置基準の大綱化にある。設置基準の緩和、自由化が進められ、新設校の設立や既存大学の新学部の創設、短期大学の四年制化などが相次ぎ、定員数が増加した。
その目的は高等教育の拡大により、国際的に活躍できる人材を育成することなどが主である。特に女子の進学率の上昇が顕著になり、大学進学においてはかなり男女の平等化が進んできて、東京都などでは女子の進学率の方が男子を上回っているほどだ。果たして企業の採用においては、そこまで男女の平等は進んでいるだろうか。
日本は大学には入りやすくなったが、就職という出口の厳しさは以前と変わらず続いている。最後に冒頭の彼女はこう言った。「諦めなければ必ず結果はついてくると思えた経験でした」と。3年次のインターンシップから始まり、学業や部活動などと並行して頑張り抜く気力が問われる。少子化だから就活は楽と思ったら大間違いなのが今の日本の現状である。
(ハナマルキャリア総合研究所代表)http://hanamaru-souken.com/