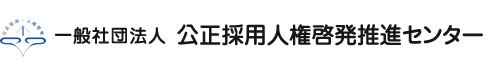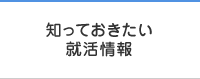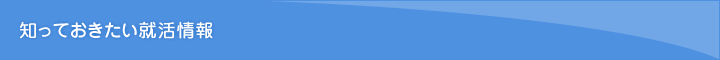【就活考転載】企業比較で広がる視野 適職選びの基準明確に 栗田貴祥(2025/10/6付 日本経済新聞 夕刊)(2025/10/14)
夏季休暇が終わり、大学では後期の授業やゼミ活動が始まった。夏のインターンシップ等のキャリア形成支援プログラムが一段落ついた今、これらへの参加が学生にもたらす影響や変化について考えてみたい。
キャリア形成支援プログラムの参加を通じて「自己理解が進んだか」「業種理解が進んだか」「企業・各種団体等を選ぶ際の自分なりの基準が明確になったか」を聞いた当センターの調査では、プログラムに参加した数によって回答の内容に大きな差があった。
「自己理解が進んだか」に対する回答では、プログラムには不参加と1社のみ参加した学生のうち「そう思う」と回答したのは36~37%だった。しかし2社以上への参加になると61.3%と、大きく数字が跳ね上がる。「業種理解が進んだか」に対しては、2社以上参加の64.6%が「そう思う」と回答した。
「自分なりの基準が明確になったか」でも、「そう思う」と回答した学生は、プログラム不参加だと31.8%、1社参加では35.4%にとどまったのに対し、2社以上に参加した学生は55.9%となっている。
決して、インターンシップ等に多く参加すべきだと言いたいわけではない。大事なのは、複数の企業や職種のリアルな情報に触れることで、それぞれの特徴や違いに気づき、比較できるようになるという点だ。
例えば同じ営業職でも、法人営業と個人営業では、相手との関係の築き方や商談の進め方まで様々な点で異なる。企業規模や社風によっても、任される業務範囲が違ってくるだろう。
1社だけ見ていては気づけなかったことが、2社以上の情報に触れると見えてくることがある。「どちらかといえば、法人営業のほうが好きだな」など、自分の好みや向き不向きを考えやすくなるだろう。
私が取材したある大学では、キャリア教育の一環で中小企業と連携したインターンシッププログラムを実施している。そこでは、実習日数5日以上という条件で単位を付与しているが、A社で3日、B社で2日など2社以上への参加も認めているという。
複数社のプログラムに参加する学生は、結果としておのずと企業同士を比較して、自分の強みがどんな場面で発揮できるかを考えるようになっている。参加後には事後研修があり、学んだことや気づいたことを言語化する振り返りの時間を設けているのも大事なポイントだ。
比較することで、自分にとっての適職選びには、さまざまな視点があることがわかるだろう。秋や冬もまたインターンシップ等が開催されていく。就活を進めるうえで、もっと自己理解を深めたいと思っている人は、「比較」をテーマに行動していくのもいいかもしれない。
(インディードリクルートパートナーズリサーチセンター上席主任研究員)