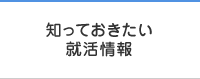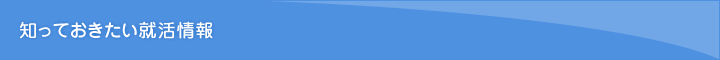【ビジネスと人権を考える】資本主義への問題提起に発展 大阪経済法科大学教授 菅原絵美(2021年11月11日付 日本経済新聞 朝刊より転載)(2022/02/03)
「ビジネスと人権」という言葉が、国連の報告書で初めて登場したのは2005年のことです。当時、「ビジネスと人権」は主に、多国籍企業の進出国で人権侵害を問題提起するために用いられました。企業と個人の問題が国連の場で取り上げられるようになったのは、こうした多国籍企業への懸念からです。
まず関心が向けられたのは、現地住民や先住民族への人権侵害です。ナイジェリアでは、石油大手ロイヤル・ダッチ・シェルの石油開発に伴う環境汚染で、その土地に暮らす先住民族は健康、食糧、水への権利などを侵害されました。多国籍企業がもたらす経済的恩恵や政府との関係性を考えると、政府による問題解決は期待できず、非政府組織(NGO)が国連の場で訴えるようになりました。
1990年代から企業の社会的責任(CSR)を問う動きが高まり、「ビジネスと人権」の焦点もサプライチェーン、さらにはバリューチェーンへと広がりました。米スポーツ用品大手ナイキのスウェットショップ(搾取工場)問題が代表例です。製造委託先である東南アジアの複数の企業で強制労働、児童労働、ハラスメントといった深刻な問題が明らかになり、委託元であるナイキの社会的責任が問われました。
このような射程の広がりは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」でも確認されています。もとより「ビジネスと人権」の視点には、グローバリゼーションの影に対する問題提起が含まれていましたが、20年1月のダボス会議では「ステークホルダー資本主義」が提唱されるなど、現在では資本主義に対する問題提起を含む形でも展開されています。
日本では、「ビジネスと人権」という視点に戸惑う企業からの声をよく耳にします。日本企業で人権といえば、障害者、女性、LGBT(性的少数者)に対する差別、ハラスメントやワーク・ライフ・バランスなど、自社で働く人々に対する施策が中心でした。こうした施策も含めて、バリューチェーン全体でのステークホルダーから考える「ビジネスと人権」の視点が求められています。
菅原絵美(すがわら・えみ)大阪大学博士(国際公共政策)。専門は国際法、国際人権法。