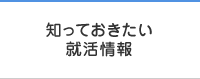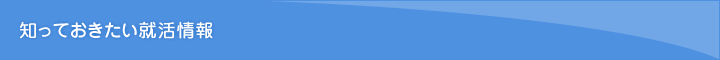【就活のリアル転載】性格検査あくまで参考 業績との因果関係、少ない 海老原嗣生(2017/9/4付 日本経済新聞 夕刊)(2017/09/11)
前回、採用選考の中で、性格面の適性検査については、企業はこれをあまり重視していない、と書いた。
その理由を今回は詳しく説明しておきたい。
性格面については、だいたい15個程度の因子について、その高低を見られるようになっている。
もう何十年もこの検査を使用している企業が多々あるため、過去に入社した人々を徹底分析する企業がけっこう現れる。
彼らは以下のような方法で、それを行う。
まず、職務別に高業績者と低業績者を集め、彼らの性格因子の構成にどのような違いがあるかを調べる。これをGood-Poor(略してGP)分析という。
ただ、高業績者も低業績者も性格的なばらつきは大きいため、それほど強い特徴は見いだせない。結局、3~4因子に緩やかな差が出るにとどまる。
これらを「高業績者の特徴」として選考に活用したとしてみよう。
たとえばここで4つの因子で、高業績者の8割が「高い」点数をとっていたと仮定する。だから応募者のうち、これら4因子の「低い」人を、自動的に不合格にさせたとしよう。
一見合理的に見える選考法であるが、この方法だと今、社内にいる高業績者の多くは「不合格になってしまう」ことに気づくだろうか?
なぜなら、どの指標でも「高い」群は8割しかおらず、2割は「低い」群に入っているからだ。
数学的に単純計算すると、4指標すべて高い人は、高業績者の4割強にとどまる。すなわち、この選考方法だと、将来、高業績者になる人の6割が落ちてしまうのだ。
こんな感じで、分析は結局、隘路(あいろ)に入り込み、参考にしか使われなくなる。
同様の研究はアメリカで1960年ごろに盛んに行われていた。多種多様な検査を活用して、有意性が高い選考手法を開発したケースも少数ながら垣間見られる。
結果はどうなったか。
高業績者の卵ばかりが並んでしまい、縁の下の力持ち的な人材がいなかったため、組織運営がかなわなかったという。
結局、組織には多様性が必要ということで、性格検査によるふるい分けは、以後、下火になったそうだ。
ちなみに、こうした性格因子による高業績者についての予測が失敗したことを、アメリカでは「グレートマンズ・セオリーの破綻」と呼んでいるそうだ。
(雇用ジャーナリスト)