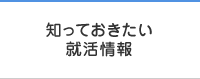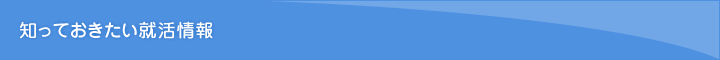【就活のリアル転載】大学進学率上昇のドイツ 職業大、ホワイトカラー系も 海老原嗣生(2018/6/19付 日本経済新聞 夕刊)(2018/06/26)
前回のこのコラムでは、欧州の大学無償化の厳しさを紹介した。それは、幼少の頃から成績と態度でふるいにかけられ大学に行くべき人を絞り、「ふさわしい人ならば貧富の差なく学べる」という仕組みを前提にしていることだ。日本のように「誰でも大学に行けるための無償化」とは全く異なる。
欧州には、無償化を巡り、もう一つの教訓がある。今回は、近年急激に大学進学率が高まったドイツを題材に見ていくことにしよう。
ドイツでは現在、高卒者の半数以上が大学に進学をしている。これだけ多いと、とても専門知識を生かせる仕事に就けはしない。もちろん社会の上澄みのエリート層にとどまることも極めて難しいことだ。多くの卒業生は、普通の企業で普通の会社員になるしかない。そこでそれに合うように、大学の形を変えた。
ドイツの大学は、大きく分けて普通大学(総合大学)と職業大学(専門大学)の2つがある。これまで技能系に偏っていた職業大学を拡充し、現在ではホワイトカラー系のいわゆる会社員養成をしているのだ。まさにその様は、就職予備校といえる。
ドイツの場合、大学は3年制だが、職業大学の1.2年だと、座学で色々な職務を学ぶことになる。それこそ、人事・経理・総務・マーケティング・宣伝・営業など5~10種の仕事に就いて、企業経験のある実務者を講師として迎え、がみがみ指導するのだ。
そして3年になると、座学で学んだ職務の中から3つを選んで、2カ月ずつ合計半年間企業実習を行う。日本のインターンのようなお気楽なものではなく、派遣社員さながらに、あれこれ言われながら、大量の伝票の処理や営業アポとりなどをさせられるのだ。そして、最後の半年は、実習した3職務から1つを選び、その振り返りを論文にする。
ちなみに、普通大学でも、ここまでではないが、座学の実務教育も企業実習もあるところが多いという。
大学生を増やすなら、社会が求めるものと齟齬(そご)をきたさない形に大学を変えるべきだという好例だろう。日本でも数年前、世界的な研究を行うグローバル人材を育てるためのG型大学と、実務密着のローカル人材を育てるL型大学とに分けるべきだ、という改革論議がなされた。
ただこの時はL型大学が技能系教育の場とされた。いや、技能系は専門学校と高専で十分だ。それよりも大学で必要なのは、普通の会社人教育の場だ。それが普及すれば、日本の就活ももう少しわかりやすいものになるだろう。
(雇用ジャーナリスト)