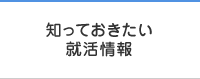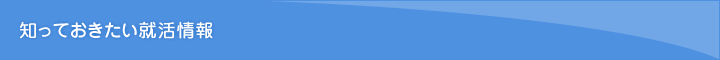【就活のリアル転載】「氷河期」招いた要因は? 大学・企業ともに経験乏しく 海老原嗣生(2021/3/9付 日本経済新聞 夕刊)(2021/03/16)
1996年、2000年、03年の就職氷河期では、卒業生の27%もが進路未定(一時的な職に就く例も含む)となってしまった。なぜこのようなことが起きたのだろうか。そこには「不況」だけではすまされない複合的な「大人たちの失敗」がある。
まず、日本では1970年代まで大学進学率は高くはなく、男性で3割程度、女性を含めて人口の2割という状況だった。つまり大学生は希少な存在だったのだ。また、経済環境もオイルショックの1年を除けば国内総生産(GDP)はプラス成長を維持しており、企業は総じて拡張傾向だった。こうした状況のため、大学の就職課は現在のような「就職サポート」をしっかりする体制を敷いていなかったのだ。
その後、大学進学率は徐々に伸びてきて男性では4割近くとなるが、この時期にはバブルが重なり、やはり就職先には困らなかった。こうした状況で、いきなり経済は絶不調となる。つまり、90年代は大学側の準備も整っていなかったといえるだろう。
さらに悪いことが重なる。当時は第2次ベビーブーム世代が大学生となる時期だった。受け皿として大学は定員・学部を増やし、新設される大学も多数あった。それだけ、経験不足の教職員も急増していたのだろう。これが2つ目の問題だ。
90年代後半になると18歳人口は減少を始める。このトレンドの中で、学生の確保に困った短大・女子大が四年制共学へとくら替えを始める。家政・幼児教育系を主としていた短大が四年制共学となり、就職指導はやはり混迷を極めた。これが3つ目の問題。
そして、90年代後半まで労働行政の主軸は高齢者と女性とされていたため、若者に対しては、ほぼ無策だった。これが4つ目の問題となる。
最後は企業の問題だが、これはこれまで何度か触れた。当時は新卒採用を一気に絞る企業が頻出した。これが5つ目の問題だ。ただ、一度そうすると、社内の年齢構成が崩れ、企業経営に様々なひずみが生まれることを知る。だから、その後に不況が来ても「一気に絞らず採用は続ける」企業が増えた。
つまり、産官学すべてが「就職氷河期ビギナー」だったことが大きな問題だったのだ。
対して、リーマン・ショック後の不況期は進路未決定者は19%程度であり、「ミニ」氷河期ですんだ。これは就活にかかわる大人たちが経験を積んで対処法を知ったからだろう。
人口構造的にも人手不足は続く。今回の「コロナ氷河期」は、リーマン・ショック時よりもさらに傷は浅くなるのではないか、と読んでいる。
(雇用ジャーナリスト)