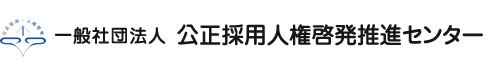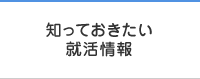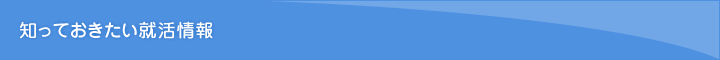【就活のリアル転載】セクハラどう防ぐ 勇気持ちクレームを 曽和利光(2025/1/21付 日本経済新聞 夕刊)(2025/01/28)
厚生労働省によるとインターンシップや就職活動中にセクハラを経験した学生(2020~22年度卒)はいずれも3割を超えている。うち約3割が不眠を訴え、約2割が通院や服薬をするまでになっている。セクハラをしたのはインターンシップでは知り合った従業員が5割弱、就活ではOB・OG訪問での従業員が4割弱などであった。コンプライアンスが叫ばれる今の社会で驚くべき数字だ。
厚労省はセクハラ防止策を企業に義務付ける準備をしているが、リクルーティングサービスのi-plugによるセクハラ防止対策の調査では企業側は「特に何もしていない」が最多の32.5%、「検討している」「開始する予定」という企業まで含めると、半数以上が対策を実行していないのが現状だ。
就活セクハラは企業の責任であるから、採用活動にかかわる者へのガイドライン設定や教育研修の実施、個人情報の利用者限定やオンラインでの接触推奨などの対策が喫緊の課題だ。
ただ、企業の遅々とした対応を待っていては、被害は止まらない。はなはだ残念なことではあるが、現時点では就活生の側も自己防衛の観点を持たなければならない。まず簡単にできるのは、口コミサイトなどで就活セクハラの情報が流れていないかの確認だ。合否に不利に働くのではないかという恐れから、被害を公に訴えられないことが多く、なかなか実態を探ることができないからだ。
また、企業がいくら対策をしていても、採用活動に公式にかかわらない一般社員には届かない。このため、OB・OG訪問をする際にはできるだけ企業が設定した公式の紹介ルートや、信頼のおける紹介者を介してのアプローチにするということも重要だ。
もし、万が一、面接や説明会、インターンシップの担当者など、公式の採用活動担当者からセクハラを受けた場合はどうすべきか。個人で対応するのでなく、いち早く大学のキャリアセンターの相談窓口などを利用して、公式なクレームを入れてもらうべきだろう。
非公式な個人的なクレームであれば、ひっそりと不合格にして隠蔽することもしやすい。公式のクレームなら、その後の合否に関しての影響も最小限にすることができる。いずれにせよ、覚えておくべきは、対策が遅れているとはいえ、企業側が就職セクハラを容認することはないということだ。これまでいくつも就活セクハラ事件は起こっているが、実行者は厳罰に処され、企業は丁重に対応している。しかるべきルートで訴えれば、就活生に不利になることを企業はしない。
それは「偉い人」が相手でも変わらない。むしろ、企業の中で責任ある立場の人ほど失うものも大きいため、あらゆるハラスメントに敏感であるのが現代の常識だ。就活生は泣き寝入りせず、勇気を持って行動してほしい。
(人材研究所代表)