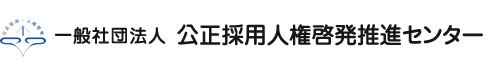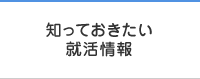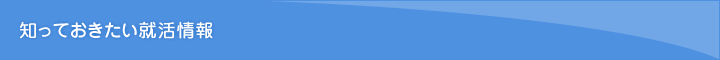【就活のリアル転載】インターン落ちたけれど 本採用は別、チャレンジを 栗田貴祥(2025/2/4付 日本経済新聞 夕刊)(2025/02/18)
昨今、就職活動の準備段階として、インターンシップ等のキャリア形成支援プログラムに参加することが主流になっている。2026年大卒予定者の参加率はすでに8割に迫る一方で、「インターンシップの選考に落ちたら、採用の本選考も受からないのではないか」と不安を抱える学生は少なくない。
リクルート就職みらい研究所が25年卒の大学生に、インターンシップ等の選考を通過できなかった企業について採用選考を受けたかどうかを聞いたところ、89%が「受けなかった経験がある」と回答している。また、インターンシップ等の選考結果が採用選考に影響を与えると考えている学生は70.3%に達した。
では学生はなぜ、インターンシップ等の選考結果が採用選考に影響すると思うのだろうか。その理由を実際に学生へ聞いてみたところ、半分以上の学生が「なんとなく自分がそう思っているから」という感覚的な理由だと答えた。逆に「影響はないと思う」という学生で多かったのは、「企業の人事担当者から聞いたから」という回答だ。
これらの学生の声をもとに考えてみると、学生自身が自らの思い込みや情報不足による誤解から、採用選考に進めたかもしれない企業の選択肢を、自ら狭めてしまっている可能性があることが分かる。
インターンシップ等の開催は、企業にとって人的にも物理的にも負荷がかかる。企業側も社内のリソースが限られているため、学生の受け入れ人数の上限を設けざるを得ず、結果的に、選考の倍率が高くなってしまうこともあるだろう。
つまり、インターンシップ等への選考の当落は、受け入れ側のキャパシティー上やむを得ず人数を絞った結果であることも多い。このような背景があるからこそ、インターンシップ等の選考に落ちてしまったからといって、必ずしも本選考も門前払いになるというわけではないのだ。せっかく開かれているチャンスに、自ら背を向けてしまうのはもったいない。
「適性がない」「この企業から求められていない」などと落ち込むことなく、ぜひ採用の本選考にも前向きにチャレンジしていってほしい。不安があれば、その企業の人事担当者に直接質問してみてもいいだろう。
そして企業側は、学生の懸念払拭のために、インターンシップ選考の結果が本選考に影響しないというのであれば、そのことを明確に学生に伝えるべきだ。学生が納得感のある進路選択を行えるよう、透明性の高い情報提供とサポートは欠かせない。
企業側が学生に対し、「もし、インターンシップに参加できなかったとしても諦めず本選考に来てほしい」とメッセージを発信すれば、インターンシップ等では出会えなかった多様な学生との接点を増やせるはずだ。
(リクルート就職みらい研究所所長)