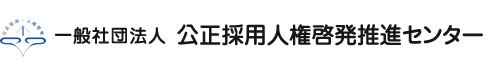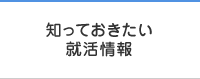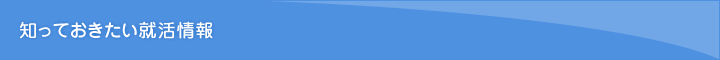【就活のリアル転載】3年以内の離職率約35% 学生は就活の質高めよう 曽和利光(2025/2/18付 日本経済新聞 夕刊)(2025/02/25)
大学の新卒入社(2021年)の34.9%が3年以内に離職していることが厚生労働省の調査でわかった。これは直近15年間で最大だ。企業は離職防止努力はしている。採用基準を精査し、面接担当者にトレーニングを施し、管理職にマネジメント力向上研修を実施している。しかし、残念ながら数値が改善される様子はない。
ただ、離職の増加は企業だけのせいではない。学生の側が自分に合う会社を見誤っているという側面もある。自己分析や企業研究が曖昧であれば、「なんとなく」合っていると思う会社を受け、深い吟味をせず入社する。当然ミスマッチとなりやすい。売り手市場で内定が取りやすいので、そんなことも起こりうる。
もうひとつ気にかかるのが、そもそもの学生の就職活動量が年々減っていることだ。リクルート就職みらい研究所の「就職白書2024」によれば、最近はOB・OG訪問を約15%の学生しかしていない。また、プレエントリー(連絡先などの個人情報を送り、企業から採用情報を得ること)は約28社だ。以前は100社ほどが常識とされていたこともあった。
そして、個別企業・各種団体などの説明会参加は対面とオンラインを合わせても約18社、エントリーシート提出が約13社である。それでもその中から約2.6社も内定を得ることができている。内定をもらえているのだから、学生は就活量が少ないとは思わないのだろう。
学生の本分は学業である。以前は大学側から「学生に就職活動の負荷がかかりすぎている」というクレームが経済界に入っていたほどなので、「就活が楽になってよかった」とも言える。
しかし、冒頭の3年以内離職率の増加を思うと、もしかすると「少なすぎやしないか」とも思う。何百万もある会社の中でわずか10社超だけで、本当に自分に合った会社や仕事がどんなものかを、ちゃんと比較検討できるだろうか。
「いろいろ考え抜いた上で、自分でこの会社に決めた」という相応の覚悟を持ってこそ、入社してから腹をくくって仕事にまい進できるもの。どんな会社や仕事でも理想と現実のギャップや困難や苦労はあるものだが、その時に「でも自分で決めたのだから頑張ろう」と思うのか、「もっと他に自分に合ったところがあったのかもしれない」と思うのかではかなり違う。
単純に「受ける会社を増やせ」とは思わない。量を増やさずとも就活の質を高めることはできる。適性検査などで自分に合う会社を見つけたり、企業の採用ページやSNSでそれほど時間やコストをかけないで情報収集したりできる時代だ。
売り手市場だからと漫然と就職活動をすることなく、手法はなんでもよいので納得いくまで取り組むことで、大事なファーストキャリアを不本意に早期離職することがないよう祈るばかりだ。
(人材研究所代表)