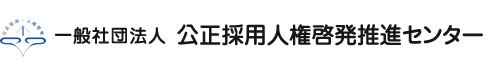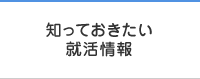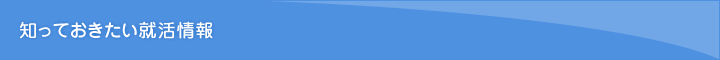【就活のリアル転載】形骸化する解禁ルール 就活長期化の害大きく 曽和利光(2025/3/11付 日本経済新聞 夕刊)(2025/03/18)
3月1日、就職活動が解禁された。しかし、リクルート就職みらい研究所の調べでは、既に2月1日時点で約4割の学生が内定をもらっており、約2割の学生が就職活動を終えている。このように、年々企業の採用活動は早期化しており、政府が要請している採用活動ルール(あくまで要請であり、企業側の自主規制ルールは既に撤廃されている)は完全に形骸化していることがわかる。
ただ、就職活動の早期化については、私は特段問題とは思っていない。学生の長期休暇などを利用して、インターンシップや会社説明会、選考などを行うのであれば、学業を阻害することはない。学生も3年生の間に進路が決まるのであれば、最終学年は研究や卒業論文、クラブの大会などに全力投球できるわけなので、むしろ早期化はうれしいのではないか。
それよりも、学生の害になっているのは企業によって採用活動の時期が分散する「長期化」ではないか。例年、最も早期に採用活動をするのは、決まって外資系企業やメガベンチャーと呼ばれる新進大手企業だ。それらの企業の学生の人気は高い。
一方で、経団連に所属する日系大手企業は、一部は早期に採用活動を行うものの、メインの活動は3月1日の解禁後にしていることが多い。日系大手企業の人気も依然として高い。
この2つの人気企業群の採用時期が分かれていることで、学生は困っている。たとえば外資系コンサルティング会社と日本の総合商社の両方を希望している学生は、同時期に就職活動をして比較検討することができない。商社を受けずして外資に決めるか、外資の内定を蹴って商社に臨むか(しかし商社に合格するかはわからない)という究極の選択を迫られる。追い込まれて、外資の内定を持ったままこっそり商社を受けるという、つきたくもない噓をつかねばならない。かわいそうな状況だ。
それもこれも、政府や企業が完全に形骸化している就職活動ルールを建前だけ掲げていることが原因だ。このようなルールは完全に撤廃してしまい、日系大手企業も堂々と外資系企業やメガベンチャーなどと同時期に採用活動ができるようにすればよいのではないか。そうすれば就活生は上述のような理不尽な悩みを持たずにすむ。企業もこそこそ採用活動をせずにすむ。
早期化の懸念は、もともとは「学業を阻害する」ことから始まった。ゼミや授業を就活のために休む学生が続出したからだ。また、最近の売り手市場で学生の就職活動量は激減しており、学業を阻害する採用活動をしている企業には人は集まらない。
実際、企業は「集客」のために週末や夜間、長期休暇に採用活動をするようになっている。つまり、おおよそ早期化の懸念など、もう存在しないのだ。早期化の亡霊から早く逃れて、正常な就活市場をつくってほしいものだ。
(人材研究所代表)