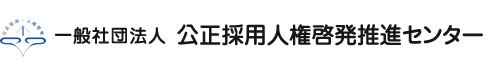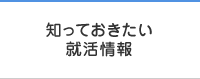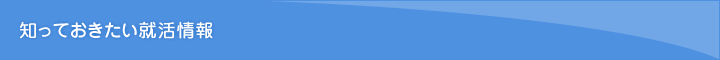【就活のリアル転載】オワハラが起こる理由 口説くには信頼関係必要 曽和利光(2025/4/1付 日本経済新聞 夕刊)(2025/04/08)
内定を出した学生に他企業で就職活動をしないよう迫る「オワハラ」防止を徹底するよう、政府が経済団体等に要請した。企業が親の同意を確認する行為「オヤカク」の禁止なども求めた。2027年3月卒業予定の学生などが対象で、職業選択の自由を考えれば当然のことだ。
たとえば、内定を出した自由応募の学生に、後から本来不要なはずの学校推薦を要望する(そのことにより辞退できないようにする)とか、密室で学生に「今ここで各社に辞退連絡をすれば内定を出す」と迫るなどはわかりやすい例だ。
ただ、多くのハラスメントに通ずることだが、ライン引きは難しい。企業が優秀な候補者に「ぜひ自社に入ってほしい」と口説くのは普通のことでもある。ただ、それを相手が脅迫や威圧に感じたりするとオワハラになる。それを恐れて、「うちは内定を出しますが、あとはあなたが自分で決めてください」と採用担当者は徐々に口説かなくなってきている。
この状況は、学生にとってすべて喜ばしいことだろうか。世の中をまだ知らない多くの学生は、会社や仕事をどう決めればよいか悩んでいる。企業からのアプローチは「この会社は自分をどのくらい、なぜ必要としてくれているか」を知るための重要な情報でもある。
「行きたい会社」に入るのもよいが、「自分を求めている会社」に行くとうまくいくことも多い。請われれば意気に感じるのが人間というものだ。そう考えると、早々に内定を得て就活を終える学生は口説かれる機会を失っているともいえる。
思うに、結局のところ、企業の採用担当者が学生と信頼関係を築けていないので、普通の「口説き」が「ハラスメント」になるのではないか。よく知らない謎の人物に「うちに来てくれ」と迫られれば怖い。しかし、互いに理解しあっている人から「一緒に働きたい」と言われるとうれしいのではないか。
そうであれば、採用担当者がオワハラを避けるためにすべきことは、責任から逃れるために口説かないことではなく、相互理解を深めて学生と信頼関係を築くことだ。ちゃんと信頼関係を築いていれば、学生は自分のことを思って真剣に口説いてくれる人と、企業の利己的な目的のためにこちらの都合など考えずにオワハラをしてくる人を混同することなどない。
採用担当者が信頼関係を築けないのは、仕事に忙殺され、対峙しているのが生身の人間だということを忘れているからだ。
普通、初対面では互いに自己紹介をし、本題に入る前に雑談などでアイスブレークを行ってリラックスを促し、相手に興味を持って話を聞き、話してくれたことに感謝する。それなのに学生に自己開示をせず、聞きたいことだけ詰問する人が信頼されるわけがない。こういう採用担当者がオワハラを起こしているのだ。
(人材研究所代表)