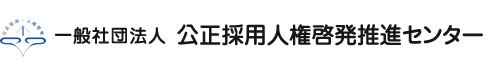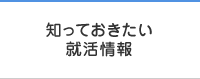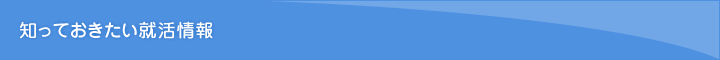【就活のリアル転載】早期離職防ぐには キャリア、じっくり対話を 栗田貴祥(2025/5/20付 日本経済新聞 夕刊)(2025/05/27)
新年度がスタートして1カ月半がたった。新たな生活スタイルに少しずつ慣れてきたという新卒社員も多いだろう。一方でこの時期に話題になるのが、入社直後やゴールデンウイーク明けに早期離職するケースだ。
大卒新入社員の3年以内の離職率は約3割といわれてきた。厚生労働省のデータを見ても、過去20年で3割前後で推移しており、いつの時代も一定数の早期離職は生じている。では、昨今の早期離職に特徴的な変化として、どのようなものが考えられるだろうか。
変化の一つに挙げられるのは、転職が一般的になったことだろう。慢性的な人手不足により企業の採用意欲は高止まりしている。面談や面接のオンライン活用が進み、情報収集や企業との接点を持ちやすくなったことから、「社外にもキャリアの選択肢がある」という認識が当たり前になりつつある。
また、仕事は「あくまでも人生の一部」という価値観も広がっている。「生活を豊かにする趣味や家族との時間を大切にしたい」など一人ひとりの多様な人生の優先順位が尊重され、自分らしい生き方が実現できない職場環境ならば、違う選択肢を探しに行こうとする動きは当たり前のようになってきている。
今ある業界や企業がこの先どうなるか分からないという不確実性の高い時代ゆえに、「何が起きても生きていけるような力をつけたい」「キャリアの主導権を持てる環境に身を置きたい」と考えるのも当然の変化だといえるだろう。
そんな新卒社員を迎える企業に求められることは何か。大切なのは、採用選考時から一人ひとりの将来のキャリアに向き合うコミュニケーションだ。就活の早期化により、自己理解・企業理解が深まる前に進路決定してしまう学生は少なくない。相互理解が不十分であるほど、「思っていた職場・仕事内容と違う」というショックが生じ、早期離職につながりやすい。
そもそも、開示されていた求人情報と実態が明らかに違っていたり、ハラスメントのある職場で心身の健康に悪影響があったりと、早急に環境を変え次のステップに進むべきケースもあるため、早期離職が一概に悪いものだということはできない。
ただ、本来互いに深めておくべき対話がなかったことで生じるミスマッチが早期離職につながっているのであれば、これほどもったいないことはない。希望通りではない配属先だとして離職に至るケースもあるが、学生の視点では見えていなかったキャリアが広がり、強みが引き出されることもある。
企業はどんな思いで配属を決め、個人に何を期待し、中長期的にどんなキャリアの可能性を見据えているのか。丁寧に説明し話し合える関係性を作っていくことが、本意でない早期離職を作らない一番の近道になる。
(インディードリクルートパートナーズリサーチセンター上席主任研究員)