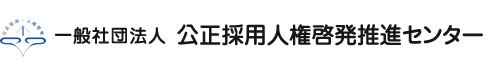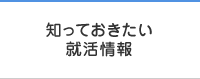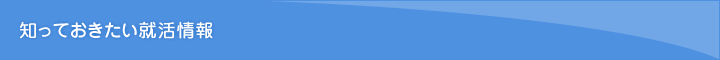【就活のリアル転載】曖昧な採用基準 ミスマッチの温床に 曽和利光(2025/5/27付 日本経済新聞 夕刊)(2025/06/03)
どんな会社でも人を採用しようと思えば、最初に考えるのは求める人物像や採用基準だ。
これらがはっきりしなければどんなスケジュールで採用活動をすればよいか、どんなチャネルで採用広報を行えばよいか、自社のどんなところを魅力として訴求すればよいか、適性検査や面接、グループワークなど、どんな選考手法を取ればよいか、すべて決まらないはずだ。
ところが、残念なことに多くの会社の採用基準はいまだに極めて曖昧だ。たとえば、よく使われる「コミュニケーション能力」など、一体何を言っているのかわからない。
「論理的に話せること」「空気が読める」「表現力がある」「対人関係がうまい」など、使われ方は様々だ。他にも「挑戦心/チャレンジ精神」は、「好奇心が旺盛」「フットワークが軽い」「高い目標をやりきる達成意欲が強い」など多様だ。「協調性」は「周囲に自分を合わせてチームワークができる」「周囲と話し合って合意形成ができる」など、すべて違う意味で使われているのが現状だ。
ある会社では「主体性のある人が欲しい」と社長が言うので、その意味を問うと、「与えられた課題につべこべ言わずに前向きに積極的に取り組むこと」ということであった。これは「主体性」ではなく、むしろ「従属的」「素直」「従順」とでも言うべきことである。全くの正反対の意味ともいえる。
長年、人材を採用してきて、人事のプロがいるはずの企業側がこんな状態では、学生はたまったものではない。志望する企業の採用ホームページや募集要項を見て、そこに書いてある採用基準から、自分に合っているのかどうかを判断したり、エントリーシートや面接で何を主張しようか考えたりするのだが、ここまで表現が曖昧では本当は参考にならない。しかし、それでも学生は「こうではないか」と想像して事に臨むしかない。
企業の面接官として駆り出される社員の皆さんにとっても、曖昧な採用基準は苦労することだろう。多義的なふわっとした言葉で「こんな人を評価してください」と言われても、よくわからず、結局のところ直感や印象で評価することになり、そこに各自の心理バイアスが侵入することで、面接の精度は低くなる。様々な研究を見ると、あらゆる選考手法の中で一般的な面接の妥当性はたいてい最低レベルだが、「さもありなん」だ。
昨年、厚生労働省が大卒の3年以内の早期離職率が直近15年では最高の34.9%と発表したが、このようなミスマッチが起こるのも当然。ミスマッチが起こるのは、そもそもの採用基準が曖昧だからである。
そして、それを是正するのは、企業の人事や経営者の責任だ。いつまでも曖昧な基準で感覚的な採用活動をするのでなく、正確に言葉を定義し、適性検査などで数値化するなど、自社の基準の明確化を進めなければならない。
(人材研究所代表)