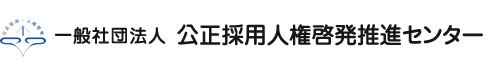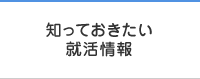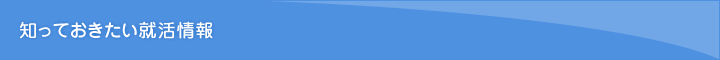【就活のリアル転載】インターンへの応募 10社程度に挑戦しよう 上田晶美(2025/6/3日本経済新聞 夕刊)(2025/06/10)
「憧れの企業か、受かりそうな企業か、どちらに応募しようか迷っています」。インターンシップの応募について、神奈川県の私立大学経営学部3年生の男子学生に質問された。6月から多くの企業のインターンシップへの応募が始まるのを前に、講義した中でのことだ。
この時期、夏のインターンシップを控え、大学3年生は「いざ就活のスタート」という機運が高まってきている。事前の準備講座が開かれる時期である。
「憧れの企業か、受かりそうな企業か」という質問に対しての答えはシンプルで「両方受けよう」。インターンシップは就活本番以上に思いのままチャレンジしてほしい。しかも「憧れ企業」に応募することでモチベーションが上がり、良いスタートが切れるという効果がある。
「憧れ企業」のインターンに参加できれば早期選考ルートに入れる可能性も出てきて、採用試験の本番に進める確率はぐっと上がる。良いことずくめだ。
それにもかかわらず、受ける前から身構えているのはなぜなのか。ひとつには試験を気にしているのかと思う。誰しも落ちるのは嫌だ。どうせ受からないのにタイパが悪い、という考えもあるのか。落ちてばかりではモチベーションが下がることも考えられる。
インターンシップは全員が参加できるというものではなく、本番さながらにエントリーシートや面接が課せられるが、企業側の受け入れ人数には限界があるので人数を絞ることはやむを得ない。その試験準備が本番さながらの練習にもなっていく。
就活を終えたある4年生が「インターンシップに参加しなかったので出遅れ感が強かった。なぜなら本番の面接で、インターンシップに参加していた学生は受け答えがうまい、慣れているな、と感じたから」と言っていた。その通りだと思う。
もうひとつ、「インターンには数多く参加できない」というスケジュール感の誤解もある。インターンシップの多くは8、9月に参加するもの。部活動やゼミ合宿の予定とかぶるかもしれない。もしもかぶってしまった場合は、もちろん大学の活動が優先である。
企業を受けるチャンスは何度かあるし、大学の講義と時期がかぶらないようにと夏季に設定しているのがインターンシップだ。それに応募した企業にすべて受かるわけではないので、受かってから考えてもよい。
また、インターンシップは5日間以上が規定ではあるが、「夏はまずは3日間。その後、秋と冬に1日ずつ」と分けて開催する企業もある。それならば2~3社は参加できそうだ。スケジュールの優先順位付けも社会人に必要なトレーニングである。本来のインターンシップは学生と企業の「ミスマッチを防ぐ」ためにある。視野を広げて、10社程度は応募してみてほしい。
(ハナマルキャリア総合研究所代表)http://hanamaru-souken.com/