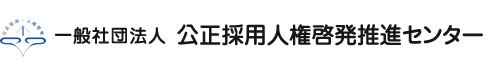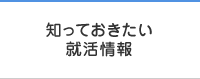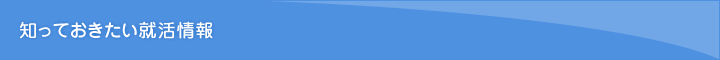【就活のリアル転載】インターンの「5日間」問題 採用に向けルール緩和を 曽和利光(2025/6/17付 日本経済新聞 夕刊)(2025/06/24)
政府は学生のキャリア形成支援についての基本的考え方の中で、「インターンシップ(汎用能力活用型)」を就業体験を含む5日間以上行うものとして定義した。この場合のみ、取得した学生情報を採用活動で利用できるとしている。そのため、多くの企業がこのガイドラインに沿って5日間の「インターンシップ」を開催し、学生を募集している。
比較的時間に余裕のある文系の学生であれば(それでも大昔と違い近年では学業に忙しいのであるが)、なんとか時間を捻出して、5日間のインターンシップに行くこともできるかもしれない。しかし、長期休暇においても理系の学生や院生、あるいは大会を控えた体育会の学生などは、研究や実験や練習などやることがとても多く、5日間もそこから離れることは容易ではない。長期休暇でも暇ではない学生も多い。
さらに言えば、求人倍率の高い売り手市場が続く現在において、5日間もの負荷を学生に課しても、応募がたくさん来るところは大手企業、有名企業、人気企業である。そんな企業が採用につながるかもしれない5日間のインターンシップを行うとなれば、学生は学業を犠牲にしてでも、行かなければと思うのは当然であろう。実際、そのようになっている。
もともと就職活動について政府や大学の主な関心事は「学業を阻害しない」ということではなかったか。企業に自由に採用活動を行わせれば、学生の学業上の都合を考えないということで、様々な規制や要請を作っているのではないか。しかし、5日以上実施しなければ採用活動につながる「インターンシップ」とは見なさないというルールは逆効果である。
もちろん、実際に学生のキャリアについての考え方に役立つような「インターンシップ」を行うためには、時間をかけて、実際に働く時と同じような業務を体験した方がよいのは決まっている。しかし、社会人になれば仕事など毎日するわけで、学生時代にしかできないことの方が、学生には重要ではないか。
生き残りをかけて日々激烈な競争をしている企業は、単なるボランティアや社会貢献のみで学生のキャリア形成支援など行わない。表面的にどのように言っていようとも、自社の採用活動、広報活動の一環としてやっている。なので「こうすれば、採用につなげてもよい」というルールには従う。
参加可能な人のために、5日間のインターンシップを実施するのはよい。しかし、そうでなければ「採用につなげてはいけない」というルールが問題なのだ。
企業が実施するほぼすべての学生向け施策は「採用目的」なのだから、どんなイベントでも採用につなげてよいとする方が噓がない。その方がもっと短い採用直結型インターンシップも増えて、学生の負荷は減るだろう。
(人材研究所代表)