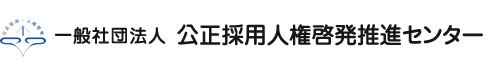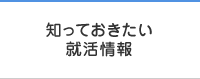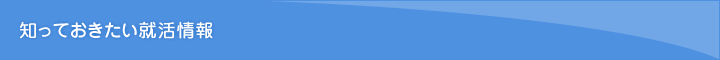【就活のリアル転載】インターンどう選ぶ 「体験ひも付け方式」検討を 上田晶美(2025/7/15日本経済新聞 夕刊)(2025/07/22)
「あらゆる業界を見ておかないと不安なのですが、全業界のインターンシップに行くことはできるでしょうか?」。インターンシップの応募に関して、神奈川県の私立大学の女子から相談を受けた。真面目な人だと思うが、あらゆる業界のインターンシップに行くというのは、もしも1年生から企業説明会であるオープン・カンパニーに参加したとしても、なかなか難しいのではないかと思う。
では、そもそも「あらゆる業界」というのは何業界くらいあるのか。政府の統計分類である日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)によると、農業・林業の第1次産業からスタートして20分類の業種がある。学生の就職が少ない農林業や漁業を除くと18業界。18社なら行けそうな気もするが、その18分類も細かく枝分かれしていき、総数では何百という業界になる。こうなると道は遠い。やはりすべての業界のインターンに行くというのは不可能といわざるを得ない。
「すべての業界を見ておかないと不安」というのは、真面目だともとれるが、根底にあるのは「やりたいことが見つからない」ということだと思われる。
インターンシップというのは自分の適性を探るために職業体験をするものだが、日数がかかるし、早期選考に結びつく可能性があると考えると、ある程度方向性を決めて、絞っていく必要があるだろう。その際、私がおすすめするのは「体験ひも付け方式」である。
これまでに活動してきたものにひも付けて業界を見ていく方法だ。学業、部活動、アルバイトなど、体験してきたことに関連する業界を検討してみる。少なからず興味を持って取り組んだ分野から広げてみてほしい。
逆にわざわざ不得意な業界にインターンに行ってみることを試した人もいる。「ITは苦手意識があるが、この時代、取り組まなくてはならない分野だと思う。一社だけインターンに行ってみたところ、簡単なプログラミングなどが出てきたが、やはりついていけなかったので、仕事としては無理だとわかってよかった」そうだ。苦手の再確認である。
インターンシップの前にやりたいこと探しやその検証はできるだけしてほしいが、「やりたいこと」は年齢とともに変化することも多い。例えば若い頃はファッションに興味があったとしても、子どもを産むと他の視点が生まれるなどである。また取り巻く環境の変化、産業の変遷も起こる。例えばデジタルトランスフォーメーション(DX)関連の仕事はここ5年くらいで広まった分野である。
転職が比較的自由にできるようになった現代では、やりたい仕事は移り変わっていくものだととらえ、今この時点の経験範囲で最善解を見つけて前進してほしい。
(ハナマルキャリア総合研究所代表)http://hanamaru-souken.com/