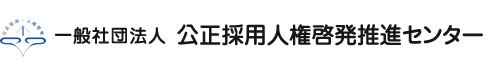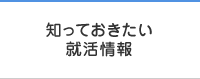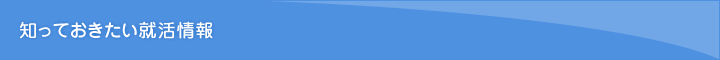【就活考転載】「仮置き就職」でいいのか 本気で足元固めを 曽和利光(2025/7/28付 日本経済新聞 夕刊)(2025/08/08)
「3年くらい働いたら転職するつもり」「まずは経験を積む場所として」。こうした言葉を就活生から聞く機会が増えている。かつて「内定」は人生の安定や将来設計の礎であり、特別な重みを持つ言葉だった。いまやそれは「キャリアの仮置き」「第1ステップ」という捉え方に変わりつつある。
転職そのものは悪いことではない。誰にも職場環境や能力・価値観の相性からキャリアを見直す場面が来る。筆者も新卒で入った会社を数年で離れた経験がある。ただ、それは仕事に打ち込んだ末の選択であり、最初から辞めるつもりではなかった。
はたして、最初から「いつか辞める」と会社を選ぶ姿勢はよいのだろうか。自身の仕事での学びを浅くし、社会人力を定着させることを難しくするのではないか。能力開発には一定の時間が必要だ。どんな仕事でも全体像が見えてくるのはプロジェクトが一巡する頃であり、たいがい1、2年以上はかかる。
さらに、自分なりに工夫をしながら仕事を改善し、責任ある立場で判断を下せるようになるには、組織内で信頼を得てからの話であり、時間をかけた人間関係の構築が欠かせない。
また、「暗黙知」という言葉もある。実務の中でしか身につかない言語化されにくい技能のことだ。これは短期の学習では得られにくく、同じ組織での上司や同僚との協働によって徐々に転移されていくものだ。腰を据えて働くことによってしか得られない能力というものが、確かに存在するのである。
さらに言えば「どうせ辞める」といった気持ちで仕事に臨めば、目の前の職務への責任感や貢献意識も育ちにくい。企業からすれば、人材が短期間で辞めてしまうことで、育成効率が下がるだけでなく、人を育てようとする士気にも影響を与えかねない。組織にとっても、本人にとっても、良い循環ではない。
もちろん、職場がどうしても合わず、成長できる余地がないと感じるなら、転職という選択肢自体はやむをえない。ただ、それは「ある程度やってみた上での結果」として判断すべきで、キャリアの判断とはやりきった先にこそ得られるものだ。
就職活動はキャリアの第一歩である。だからこそ、その一歩を「とりあえず」で済ませるのではなく、自分が本気で取り組める場所、土台となる環境を選んでほしい。たとえ後に別の道を歩むことになっても、腰を据えて働いた経験はその後のあらゆる挑戦を支える「根」となる。
「石の上にも三年」という言葉は古臭く聞こえるかもしれないが、キャリアにおける成長とは、短期間で刈り取れる果実ではなく、耕し続けることで実るものだ。目まぐるしく変化する時代だからこそ、足元を固めることの意味が問われている。
(人材研究所代表)