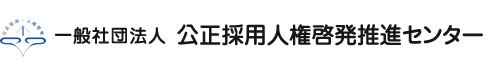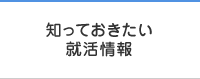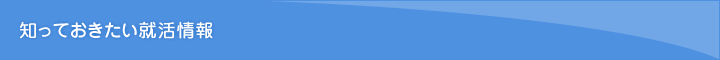【就活考転載】選ばれる企業になるには キャリア形成の支援を 栗田貴祥(2025/8/18付 日本経済新聞 夕刊)(2025/08/25)
大学生は夏季休暇も半ばを迎え、インターンシップ等のキャリア形成支援プログラムが山場に入っている企業も多いだろう。依然として学生への追い風が続く中、学生との接点を通じていかに「選ばれる企業になるか」は、どの企業にとっても喫緊の課題になっている。
2025年卒の採用では、当センターの調査によると採用充足企業が37.2%だったのに対し、未充足企業は60.3%だった。業態や企業規模など様々なため、充足率に影響する要因を特定することは難しい。その前提に立った上で、企業の「学生個人に向き合う姿勢」という観点から、充足企業と未充足企業との違いを考えてみたい。
25年卒の採用実施企業に、社内制度の社員の利用状況を聞いたところ、異動やキャリア形成の希望を伝える「自己申告制度」や「上司とのキャリア相談」の利用率が、採用充足企業のほうが未充足企業よりも8~9ポイント高いことがわかった。
入社後に社員一人ひとりのキャリアや働き方を手厚く見てくれる環境があり、考える機会や選択肢があることが、採用充足によい影響をもたらしている可能性がある。
不確実性の高い社会で育ってきた学生の中には「将来の不確実性をできるかぎり極小化したい」と考える人も多い。そのため、インターンシップで入社後のイメージを具体的に持てるかどうかや、内定後に初任配属先の部署や勤務地を確約してくれるかどうかを重視する傾向が高まっている。初任配属先の確約採用を掲げる企業が増えてきているのも、そうした学生の志向の変化が背景にあるだろう。
一方で、中長期的には結婚や出産などライフイベントの状況に応じて働き方やキャリアパスを選択していきたい学生も多い。個人のキャリアを支援する機会や制度があり、今後のキャリアについて、コミュニケーションをとれる環境が充実しているかどうかが、選ばれる企業になるためにますます重要になっていきそうだ。
「希望した部署で働きたい」という学生の意向を受け、新卒社員向けの公募制度を導入した大手保険会社の事例もある。
この制度では、募集ポストに従事している社員が内定者に業務内容を伝え、行きたい部署があれば、入社前の段階で応募して面接を受けることができるという。
公募ゆえに学生の希望が必ず通るわけではない。しかし、具体的な選択肢を前にキャリアの可能性を考える機会があることで、入社後により働きがいを感じてもらえるのではないか、と担当者は期待を寄せる。
企業が入社後の個人のキャリアにどれだけ向き合おうとしているか。その姿勢を、学生はこれからも注視していくのではないだろうか。
(インディードリクルートパートナーズリサーチセンター上席主任研究員)