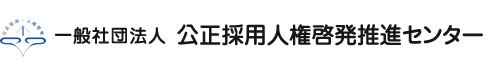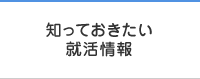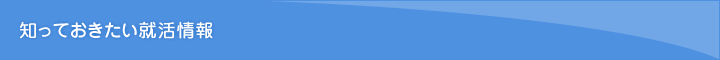【就活考転載】「仮置き就職」大企業入社で幸せか 報酬は市場価値で決まる 曽和利光(2025/8/25付 日本経済新聞 夕刊)(2025/09/01)
就活生の人気はいつの時代も大企業に集中する。知名度が高く、入社したことを周囲の人からも喜ばれやすい。過去の資産の蓄積やスケールメリットで生産性が高いため、平均的な報酬も高く、福利厚生も充実している。社会に影響力の大きい仕事をすることもあり、やりがいを感じることも多そうだ。
もちろん、その分入社は難しい。リクルートワークス研究所の最新調査では、300人未満の企業の求人倍率8.98倍に対し、5000人以上の企業は0.34倍。つまり希望者3人に1人しか入社できない狭き門となっている。雇用者全体で見ても1000人以上の大企業で働いているのは4人に1人程度だ。
では大企業に入社したら、それで「人生勝ち組」などと言えるだろうか。もちろん、人の幸せには様々な軸があるので一概には言えない。そこで近年の就活生の会社選びの軸として上位に挙がる給与で考えると「大企業に入社=高収入」とは必ずしも言えない状況が見えてくる。
独立行政法人経済産業研究所の調査(2003~07年度)によると、総賃金格差の拡大のうち「企業内格差」が主要因であり、男性では格差拡大の約82%を企業内格差で説明できるとしている。企業間格差の影響は限定的であった。
また、コンサルティングなどを手掛けるウィリス・タワーズワトソンの調査では22年までの10年で社長の報酬は中央値が20%超増えたのに対し、従業員の平均報酬(上場企業)の増加は3~12%程度と伸び率に顕著な差があった。これらの結果は「どの企業に入社するか」よりも「入社した企業の中でどのように評価されるか」の方が、給与水準を左右する割合が大きくなってきたことを示唆している。
背景には、中途採用市場の流動性が高まっていることがありそうだ。リクルートワークス研究所によれば、24年度下半期で中途採用を実施または実施中の企業は83.3%だった。その10年前の63.8%から約20ポイント増と、中途採用が急速に当たり前になってきたことがわかる。
人材市場の流動性が高まれば他の企業に人材を取られないように、個々人の報酬は需給関係による市場価値に収斂(しゅうれん)される。つまり、大企業であろうが中小企業であろうが実力さえつけておけば、市場価値レベルに見合った報酬がもらえるはずということだ。逆に、市場価値の低い人材にまで高い報酬を支払う必要はない。だから、大企業でも低い報酬の人がいるのだ。
大企業と中小企業は働き方や必要な能力が異なり、どちらが自分と相性がよいかは人によって異なる。結局、自分に力をつけることが市場価値を高め、高い報酬にもつながるのであれば、大企業をとにかく目指す必要性は薄れる。最も自分を成長させてくれる場に身を置くのがベストではないだろうか。
(人材研究所代表)