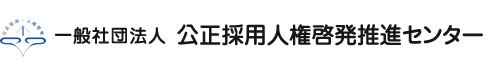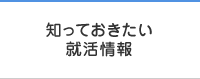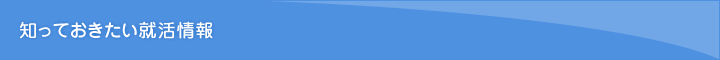【就活考転載】AI活用し学生がつく噓 原因は採用する側に 曽和利光(2025/10/20付 日本経済新聞 夕刊)(2025/10/28)
マイナビの調査では2024年大卒・院修了の就活での人工知能(AI)利用率は18.4%だったが、26年卒では66.6%と2年で3倍超に急増している。生成AIの登場で学生は「面接で話を盛る」どころか、自分で文章を考える必要すらなくなった。
「サークル活動で後輩育成に力を入れた経験をもとに、リーダーシップと課題解決力をアピールするエピソードを作って」と指示をすれば、AIは数秒後に論理的かつ構成の整った文章を生成する。さらに「同様のエピソードを異なるジャンルで出して」と指示すれば学園祭、アルバイト、ボランティアなど、幅広いジャンルと資質に対応したエピソードまで生成される。
もはや学生は何を書くかすら悩む必要がない。AIが出力した中から印象の良いものを選び多少自分の体験に寄せて調整すれば、うまい「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」が完成する。誰でも簡単に印象操作できるようになってしまった。
エントリーシートや面接でのエピソードがどれほど感動的でも、それが学生自身の体験に基づいた事実という保証はない。AIで「矛盾のない物語」が構築されていれば、面接官はそれを見抜くすべがほとんどない。
履修データセンター(東京・港)が24年に実施した新卒採用に関する調査によれば、25年卒予定の学生約600人のうち約半数が、就活では面接などでエピソードを「8割以上の学生が脚色している」と見ていることが明らかになった。
しかし、学生を責めるつもりはない。彼らはやりたくてやっているわけではない。ある人は「正直に書いたら地味で書類選考に通らない」「盛るのは意味がないと思う。入社後にバレるかもしれないし疲れる。でも、選考に上がれないからやるしかない」と語った。
この感覚は「就活における苦しみ」の核心だ。面接の帰り道、心のどこかで「本当の自分を見せられなかった」と落ち込む。何度も何度も演技を繰り返し、疲弊していく。
私は、これはオトナである企業側、採用側の責任であると思う。構造化面接など、事実を丁寧に確認できるインタビュースキルを獲得できているか。成績表や履修履歴によって、確実なファクトに基づいて学業の話を聞いたり、適性検査やワークサンプル(実際の仕事をやらせてみること)など、面接以外の精度の高い選考手法を用いたりしていれば、学生はわざわざ噓をつく必要がない。
そういう工夫をすることなく「学生は面接で噓をつく」「なんということだ。もっと誠実に取り組んでほしい」などと、被害者のようにふるまっている場合ではない。世の中の多くのことはたいてい個人に起因するのではなく、取り巻く構造に起因する。その構造を作り出しているのは企業の側なのではないだろうか。
(人材研究所代表)