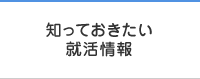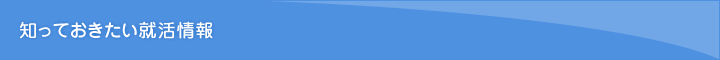【社会に出る学生のための人権入門】(第28回)人権とは? デジタル調査の時代Ⅱ(2019/12/12)
前回に引き続いてデジタル身元調査について考えていきたい。
ネット上ではビッグデータとしての個人情報が膨大な量になっており、それが恐るべきスピードで日々増加している。コンピュータの進化と各種センサーの飛躍的な増加、あらゆる機器がインターネットにつながるIOTによって、データ量が倍々ゲームで増加している。それらのデータを保存するコストも過去25年間の間に100万分の1以下になった。簡単にいえば100万円かかったコストが1円になったということである。
こうした状況は、不特定多数の個人データを重ねていけば個人を特定できる時代になったことを意味している。過去の身元調査は、興信所や探偵者が戸籍等の行政が保管している情報や、企業等が所有している個人情報を内部のエージェントを利用して違法に蒐集(しゅうしゅう)したものも使い、時には尾行等を行いながらアナログ的に進められてきた。
しかしデジタル差別身元調査は、特定個人のネット活動を分析することで、それ以上のことができるようになった。前々回紹介したリクナビの内定辞退率も就活生のサイト閲覧歴等を元にAIによって分析し、個人の内定辞退率をはじき出していた。「集団身元調査」といっても過言ではない。
デジタル差別身元調査はアナログ的身元調査と異なって、ビッグデータのAI分析も活用できるようになった。それだけではなくビッグデータとしての不特定多数の個人データを重層化することによって、特定個人の人物像を構築することも可能になっている。それらが極めて安価にできるようなり、容易にデジタル差別身元調査を行うことができるようになった。
かつて筆者が取り組んだ1998年の大量差別身元調査事件は、部落差別の身元調査だけではなく、思想信条、政党や宗教関係の新聞購読状況、労働組合への加入状況、日本に帰化している人の場合でも元の国籍等の個人データ等が調べられ身元調査の報告書に記されていた。
これらの調査対象者は、各々の企業において内定直前まで進んでいた応募者であり、そうした応募者の履歴書等のコピーを企業側が調査会社側に渡して行われていた。
差別身元調査は最後のチェックとして行われていたものであった。つまりそのほとんどが企業内部では採用内定していたにもかかわらず、調査結果で差別基準に基づいて悪い判定を受けると内定通知が該当者には出されていなかった。
このように就職差別を受けていた該当者は就職差別を受けた自覚もなく、ただ内定をいただけなかったという理解で終わっていた。まさに自覚なき就職差別の被害者になっていたのである。
今日においてもネット上の個人データで差別調査をされて排除されている自覚なき犠牲者もいるといえる。
北口 末広(近畿大学人権問題研究所 主任教授)