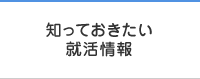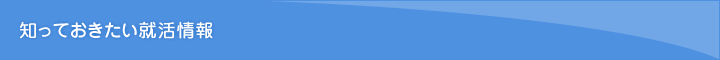【社会に出る学生のための人権入門】(第60回)情報環境の劇的な変化と人権③(2022/08/11)
前回、大学生のやる気に関わって「存在感」という言葉を使用した。「存在感」とは誤解を恐れず分かりやすくいえば「人からあてにされている(人から頼りにされている)」という感覚である。その感覚を自ら感じることが重要なのである。他の人から「あてにしているよ」といわれても本人自身が「あてにされている」と感覚なければ存在感や自己肯定感は高まらない。そのためには周りからの刺激が必要である。その刺激とは周りからの言動等の情報である。
人によって積極的な影響を与える刺激は異なる。私自身の生い立ちを振り返れば母から「あてにされている」という感覚が常にあったことを思い出す。そうした存在感が自身の自己肯定感や使命感につながった。おそらく今は亡き母は私の性格や特性を誰よりもよく理解した上で母自身の経験の中から私に数々の言葉をかけてくれた。あるいは言葉を発することなく背中で語ってくれた。母は1923年(大正12年)生まれで尋常高等小学校しか出ていなかった。それでも子育ての経験というビッグデータの中から学んだと思う。今も感謝している。
存在感や漠然とした使命感を小学生の頃からもった私は多様な「好奇心」ももった。それは学習していく上での好循環の原点になった。同様に好奇心をもった学生は積極的な意味で学問に対する疑問も生じ次々と質問し考察を深めていく。それが学ぶ好循環につながっていく。その原点ともいえる「やる気」が出てくる状況は前回紹介したように「人を見て法を説け」なのである。その際に教育活動のビッグデータを活用することができれば大きく前進するだろう。すべての人は「オンリーワン」であり同じ人はいない。人の数だけ教育手法があるといっても過言ではない。しかしそれは効率的な教育の視点からいえばかなりの無理がある。現在の公教育の現状をふまえれば個別化教育は極めて難しい。しかしAIやビッグデータを活用すれば一定の前進を図ることも可能である。今後、教育の中でビッグデータ活用を真剣に考える必要がある。そうした取り組みが人権教育のカリキュラムや教材、指導法の改善に直結する。
私が小学生のときに図書室で借りて読んだ「見えない」「聞こえない」「話せないない」という「三重苦」を抱えたヘレン・ケラーと彼女の先生であったアン・サリバンのことを著わした「奇跡の人」という名著がある。サリバン先生が行なったヘレン・ケラーへの教育は「個別化教育」の典型だといえる。彼女が自身の能力を高めることができたのは、本人自身の驚異的な努力とともに彼女の「存在感」や「やる気」を呼び起こすことができたサリバン先生の教育があったからである。
デジタル情報がビジネスの基盤となるような社会にあって、すべての分野の教育にビッグデータを活用すれば、より多くの「奇跡の人」を生み出すことができるのではないだろうか。
北口 末広(近畿大学人権問題研究所 主任教授)