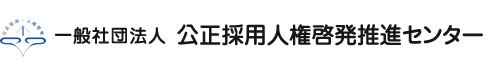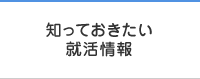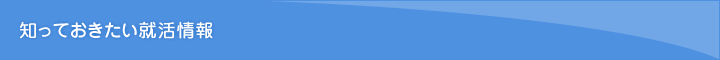【社会に出る学生のための人権入門】(第91回) SNSが与える社会への影響と人権②(2025/03/13)
前回に引き続いてSNSと人権や政治、社会について述べていきたい。SNSはフェイク情報を拡散することにも悪用されるようになった。人びとの情報交流が活発になればなるほど情報はより一層大きなパワーを持ち、プラス面でもマイナス面でも甚大な影響を与える。劇変する情報環境や人びとの情報リテラシーの力量をふまえれば、マイナス面が大きくなる可能性は高い。それを抑止できなければ民主主義は大きく後退し崩壊する。多くの人びとが信じてしまうようなフェイク情報を作成し発信することは難しいことではない。
フェイク情報を多くの人びとがなぜ信じるのか。そのメカニズムが分かっている人には多くの人びとにフェイク情報を信じさせることは容易だ。SNSは、下記の調査結果を見れば今後さらに影響力を増していくことは明らかである。
日本国内の調査である「博報堂DYメディアパートナーズ」による「メディア定点調査2024」では、1日あたり日本に住む人びとのメディア総接触時間は、2014年で385.6分で、テレビが156.9分、新聞が23.4分、携帯・スマホが74.0分という結果であった。テレビ接触時間が携帯・スマホの二倍以上あった。
10年後の昨年2024年には総接触時間が432.7分で、テレビが122.5分、新聞が9.2分、携帯・スマホが161.7分になった。携帯・スマホの接触が10年で2倍以上になった。10年前にテレビの2分の1であった携帯・スマホへの接触時間が、逆にテレビの1.3倍以上になった。メディア接触時間の主流がテレビから携帯・スマホになったのである。メディア総接触時間が10年で10%強増加しているにもかかわらず、テレビ・新聞への接触時間は約30%減少している。これはテレビ・新聞の広告収入が減少し、ネットメディアの広告収入が飛躍的に増加していることからも明らかだ。
さらに詳述すればテレビは約20%も減少し、新聞にいたっては半分以下になり10分を切っている。これらのデータに年齢的傾向を分析に加えると高齢者のテレビ視聴が圧倒的に多く、携帯・スマホは中年・若者・子ども層ということになる。同時に高齢者においても携帯・スマホ接触時間は確実に増加している。電車内で新聞を折りたたんで読んでいる人を見かけることは極めて少ない。多くの駅に流れるアナウンスも歩きながらのスマホ視聴への注意喚起が多くなっている。筆者も大学への通勤で電車に乗車しているが、20代30代で新聞を読んでいる人を見たことがない。こうした情報環境の変化が前回にも紹介したように政治や社会に大きな影響を与えている。
次回さらに掘り下げていきたい。
北口 末広(近畿大学人権問題研究所 特任主任教授)