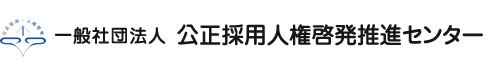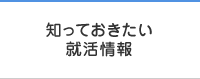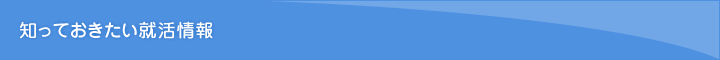【社会に出る学生のための人権入門】(第92回) SNSが与える社会への影響と人権③(2025/04/10)
前回に引き続いてSNSについて考えていきたい。高齢層は携帯・スマホよりもテレビ視聴の割合が大きいが、就活生も含めて若者の多くは携帯・スマホでテレビを視聴することはあっても家庭用テレビで視聴することは極めて少ない。中年層も徐々にテレビ視聴が減少しスマホ視聴が増加している。新聞に至ってはほとんどの若者は定期購読をしていないだけでなく読んでもいない。筆者が大学で教えている大学生もほとんど新聞を読んでおらず、講義の中で「昨日の新聞に載っていたが・・」と前置きしてもほとんど反応がなく読んでいないことが実感として分かる。
そうした状況をふまえて新聞各社も電子版を有料にして充実させているが、携帯・スマホでニュースを見ている視聴者・読者への訴求効果は芳しくない。新聞はSNSと違い、多様な世論を救い上げ、多様な課題に関してどのような選択がより良い方向かを論説を紹介しながら結論的なものに導く。しかしSNSは異なる。ソーシャルメディアの世論形成過程を分析すると情報拡散過程で情報が単純化されていく傾向が顕著である。情報が単純化・平準化され一部分だけを強調し、重要な細部が切り取られていく。そして強調化されたところだけがさらに増幅され複雑な議論はなくなる。短絡的に「黒か白か」といった短文で紹介されることがほとんどで、その結論に至るプロセスが欠落している場合が多い。これらが社会の分断に大きく影響している。こうした現象が民主主義やその基盤である選挙にも大きな影響を与えている。例えば昨年11月17日に実施された兵庫県知事選のNHK出口調査のデータを加味するとSNSが選挙に与えた影響はより一層明確だ。
「投票する際に最も参考にした情報」についての質問では、①SNSや動画サイトが30%、②テレビが24%、③新聞が24%となっており、投票行動に最も大きな影響を与えているのがSNSや動画サイトであったことが明らかになっている。これらが前回知事選の投票率を14.55%増加させるということにつながった。飛躍的な投票率の上昇である。テレビや新聞は選挙期間中の報道は政治的バランスをとるためにかなり慎重な報道になり、特定候補者が有利不利になるような報道はしないように配慮している。しかしSNSを活用した情報拡散はそうした配慮はほとんどない。そのSNSがテレビ・新聞を超えて「投票する際に最も参考にした情報」のトップになっている。それが選挙結果に大きな影響を与えた。こうした状況は選挙に限ったことではない。社会のあらゆるジャンルに影響を与えている。だからこそ情報リテラシーの重要性がより一層増しているのである。
北口 末広(近畿大学人権問題研究所 特任主任教授)