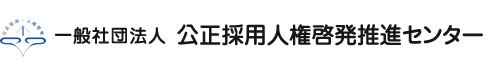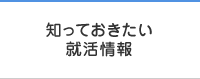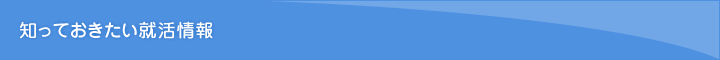【社会に出る学生のための人権入門】(第93回) SNSが与える社会への影響と人権④(2025/05/08)
前回に引き続いて昨年11月の兵庫県知事選挙を事例にSNSの影響について具体的な数字の変化を述べておきたい。知事選挙時点で兵庫県の有権者数は446万3013人であった。それに増加した投票率14.55%をふまえると、その前の兵庫県知事選挙より約65万人も投票者が増加していることが分かる。この投票者数は鳥取県や島根県の全有権者数を超える数値である。この投票者増加分が選挙結果に大きな影響を与えた。これはSNSだけが原因ではない。しかしSNSで拡散されたフェイク情報や選挙の争点設定が有権者の投票行動に大きな影響を与え、選挙結果を左右したことは紛れもない事実である。これが投票直前の世論調査においても明らかになっている。投票日の二,三日前から支持率が急激に変化していた。
今後の各種選挙においても各陣営の選挙戦術に大きな影響を与えるだろう。昨年2024年の東京都知事選挙、衆議院選挙から始まった「SNSと選挙」という問題は、兵庫県知事選挙もふまえて公職選挙法改正にもつながった。選挙は政治をリードし社会に重大な影響を与える各種議員や首長等を選ぶ民主主義の基盤である。但しSNSの情報内容や拡散の在り方は選挙だけの問題ではない。社会の各分野にも重大な影響を与えている。
電通が毎年発表している「日本の広告費」データによると2015年でテレビ広告費は1兆9323億円でインターネット広告費は1兆1594億円であった。テレビの方が約7700億円も多かった。しかし4年後の2019年には逆転し、インターネット広告費は2兆円を超えた。昨年2024年のインターネット広告費は2015年からの9年で3倍以上になり3兆6517億円になった。こうした数字が示すようにSNSの勢いが急激に拡大しているのである。情報環境の急激な変化は歴史的にも社会を大きく変えた。
一方でSNSは多くの依存症も生み出した。「いいね」や「コメント」閲覧数、シェア数で評価されるシステムであり、社会的承認欲求を通じて依存症が増加していると指摘されている。とりわけ若年世代への影響が大きいといわれている。SNS情報に対する情報リテラシーは極めて脆弱であり、誤情報やフェイク情報が拡散されることで社会が大きく混乱していることも事実だ。それが差別意識や偏見を助長し人権侵害事案の拡大にもつながっている。就活にも大きな影響を与えている。情報リテラシーの分野の中でもSNS情報リテラシーが極めて重要な課題であることを忘れてはならないだろう。
北口 末広(近畿大学人権問題研究所 特任主任教授)